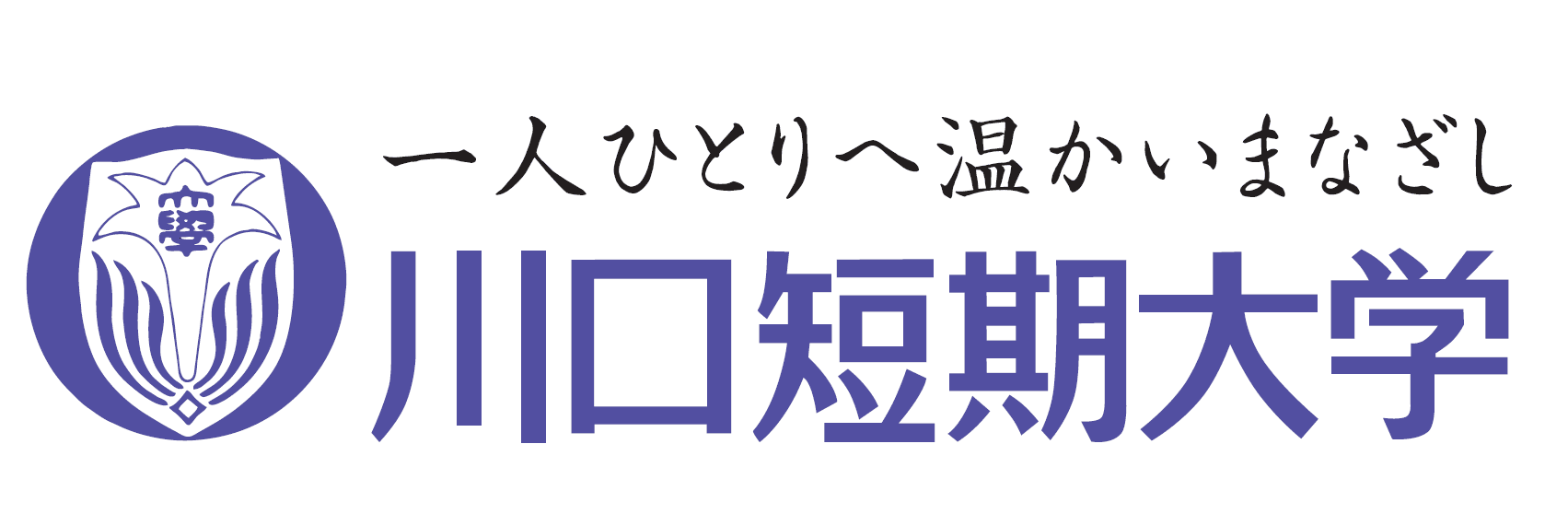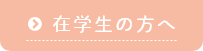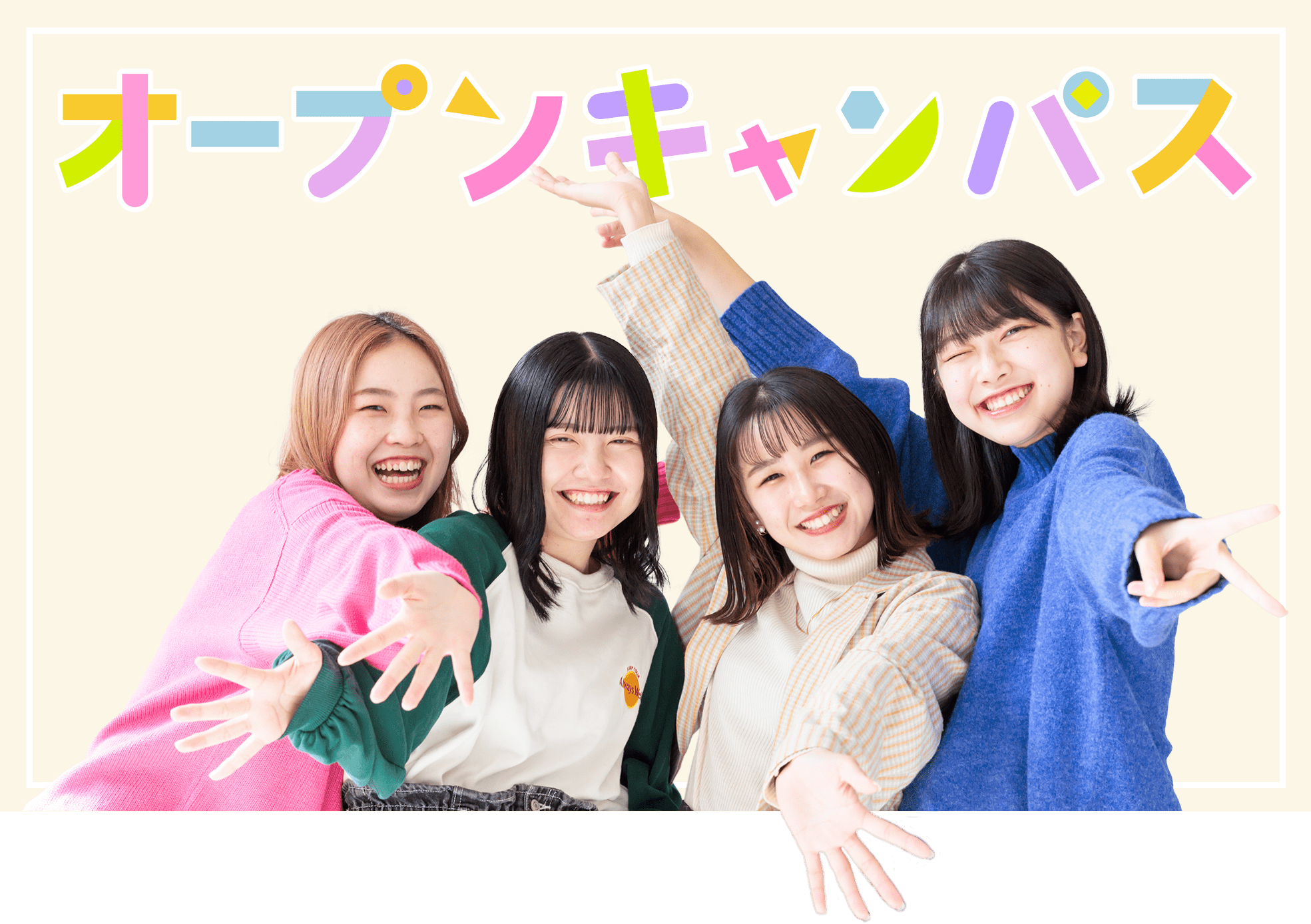ビジネス実務学科の教員を紹介します。

所属学科・職位・役職 | ビジネス実務学科 教授・ビジネス実務学科長 |
経歴 | 【最終学歴】 岩手大学大学院連合農学研究科生物環境科学専攻博士課程 単位取得満期退学 博士(農学)岩手大学 【主な職歴】 北海道教育大学非常勤講師、東京大学大学院農学生命科学研究科COE特別研究員 |
担当授業科目 | 自然科学概論、環境論 |
研究・専攻分野 | 保全生態学(環境教育全般を含む) |
研究テーマ・概要 | 環境問題解決のための調査・研究
|
主な著書・論文 | 【著書】 (共著)小島望(2016)第1章:餌付けによる野生動物への影響、第2章:非意図的餌付けと絶滅危惧種への餌付け、第18章:野生動物と人間社会との軋轢の解決に向けて、『野生動物の餌付け問題:善意が引き起こす?生態系攪乱・鳥獣被害・感染症・生活被害(小島望・高橋満彦編、畠山武道監修)』、地人書館, pp.3-17,pp.19-27、pp.279-305. (共著)小島望(2013)「環境権」「戦争と環境」「大量絶滅」など25項目, 『環境教育辞典(日本環境教育学会編)』, 教育出版 (単著)小島望(2010)『<図説>生物多様性と現代社会:「生命の環」30の物語』, 農山漁村文化協会 (共著)小島望(2010)各論・陸棲哺乳類「ナキウサギ科」, 『野生動物保護の事典』, 朝倉書店, pp.346-349. 【論文】 小島望(2015)サウンドマップが示す芸術と科学の関係性, 水月, 1:3-9. 大國眞希・安藤公美・小島望・遠藤祐(2014)架橋としての桃源境思想:関東大震災から現代, 福岡女学院大学紀要(人文学部編), 24:1-27. 小島望・長谷川理(2010)、餌づけ問題を考える.ワイルドライフ・フォーラム, 15(1):26-27. 【その他】 小島望(2017)野生動物, 『動物福祉検定初級テキストブック(公益財団法人神奈川県動物愛護協会編)』, pp.82-92. |
学会活動 | 日本生態学会、「野生生物と社会」学会、日本環境教育学会、日本環境会議、ヒトと動物の関係学会、日本サウンドスケープ協会、日本ペンクラブ |
社会貢献活動 | 公益財団法人神奈川県動物愛護協会 評議員(2013年4月~) 神奈川県鳥獣対策協議会サル対策専門部会 委員(2011年4月~) ナキウサギの鳴く里づくりプロジェクト協議会 顧問(2008年2月~) |
メッセージ | 環境問題は、「ひとりひとりができることをしよう」という掛け声では永久に解決しません。問題解決を阻んでいるのが何ものであるかを知り、その問題の本質を捉えなければなりません。そのためには情報の取捨選択や情報源となる組織や個人の背景を読み取る力、つまり、「情報リテラシー(情報を使いこなす能力)」が必要になります。私の担当する環境関連の講義では、この「情報リテラシー」が重要なテーマのひとつとなっています。 |
※誤字脱字修正(2018.11.16) |
2018.11.13付け意見書に対する環境省からの回答 (113KB) |

所属学科・職位・役職 | ビジネス実務学科 教授 |
経歴 | 【最終学歴】 明治大学大学院商学研究科商学専攻博士後期課程 単位取得満期退学 修士(会計学)立教大学 【主な職歴】 岩手県立大学宮古短期大学部経営情報学科准教授 |
担当授業科目 | 簿記Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、原価計算 |
研究・専攻分野 | 管理会計、原価計算、簿記 |
研究テーマ・概要 | 原価企画 活動基準原価計算 事象と勘定科目の関係 |
主な著書・論文 | 【著書】 (共著)『社会化の会計』(熊谷重勝・内野一樹編著)創成社、2011年10月、pp. 109-123. (共著)『グローバリゼーションと経営・会計』(高浦忠彦編著)唯学書房、2005年5月、pp.15-30. 【論文】 「仕入勘定に関する一考察」『川口短大紀要』第35巻、2022年12月 「連結集団における会社間取引の処理に関する一考察」『川口短大紀要』第35巻、2021年12月 「加工進捗度、加工換算量、および歩留に関する一考察」『川口短大紀要』第34巻、2020年12月 「先払に対する貸手側のリース会計処理に関する一考察」『川口短大紀要』第33巻、2019年12月 「複式簿記と割引キャッシュ・フロー法に関する一考察」『川口短大紀要』第32巻、2018年12月 「評価勘定と利息法で償却される社債発行費に関する一考察」『川口短大紀要』第31巻、2017年12月 「度外視法と非度外視法における直接材料費の原価按分に関する一考察」『川口短大紀要』第30巻、2016年12月 「相互配賦法と自家消費に関する一考察」『川口短大紀要』第29巻、2015年12月 「為替予約の独立処理における時価評価と期間配分に関する一考察」『川口短大紀要』第28巻、2014年12月 管理会計と財務会計の接点に関する一考察『川口短大紀要』第27巻、2013年12月 など |
学会活動 | 会計理論学会、日本会計研究学会、日本原価計算研究学会、日本管理会計学会 |
メッセージ | 逆説的に聞こえるかもしれませんが、自分に関係のない、興味のないことを学んでみてください。苦境に立った時、それが意外に役立つかもしれません。2年間がんばってくださいね。 |

所属学科・職位・役職 | ビジネス実務学科 教授 |
経歴 | 【最終学歴】 中央大学法学部 卒業 法学士 中央大学 【主な職歴】 近畿日本ツーリスト株式会社※現KNT-CTホールディングス株式会社 (千代田法人旅行支店長、中央法人旅行支店長、LUXE銀座旅行支店長ECC事業本部カンパニー販売部長、近畿日本ツーリスト神奈川社長、本社執行役員国内旅行部長、本社取締役国内旅行部長、近畿日本ツーリスト健康保険組合理事長) |
担当授業科目 | 旅行業法、観光ビジネス論、ホテル経営論、観光マーケティング論、かしこい旅行実務論、観光政策論、インターンシップ、ゼミⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ |
研究・専攻分野 | 旅行・観光業界実務 国内・海外旅行の企画・販売及び添乗業務、地方創生、イベント販売、クルーズ、マーケット開発、営業指導、社員教育、会社経営、契約機関の組織(旅館、ホテル、運輸、食事・観光施設)の運営、旅と健康、企業における健康経営など |
研究テーマ・概要 | 観光産業における地方創生・地域誘客事業(観光資源の発掘~販売と観光消費の拡大)、M・I・C・Eビジネス、夜景観光、観光産業とSDGs |
メッセージ | 旅は元気と活力を生み、お客様との喜びと感動の共有は、心も豊かにします。 観光ビジネスは、様々な沢山の新しい出会いと発見(人、自然、歴史、文化、芸術、食、動物、スポーツ、乗り物、など)があり、これらの様々な分野に普段から興味を持つ事が「楽しんで仕事が出来る」事につながり、更に探究心が自分の強みとなって業務にも活かせます。 |
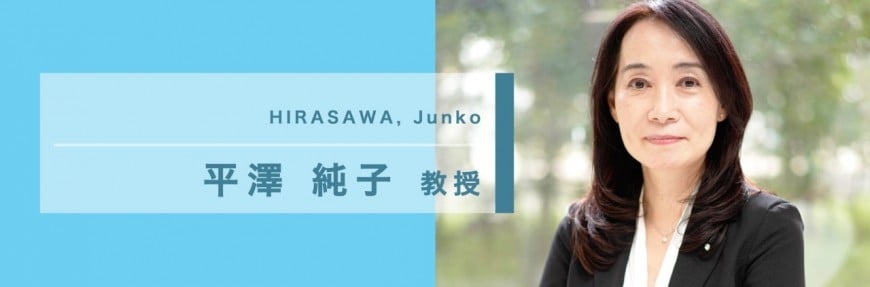
所属学科・職位・役職 | ビジネス実務学科 教授 |
経歴 | 【最終学歴】 法政大学大学院社会科学研究科社会学専攻博士課程 単位取得満期退学 修士(社会学)法政大学 博士(経営学)(シンガニア大学) 【主な職歴】 十文字学園女子大学社会情報学部 武蔵野女子大学現代社会学部 法政大学社会学部 法政大学キャリアデザイン学部において非常勤講師 東京都立労働研究所研究員 日本学術振興会特別研究員 独立行政法人労働政策研究・研修機構研究員 |
担当授業科目 | 人的資源管理論、キャリア・デザインⅠ,Ⅱ、ゼミⅠ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ |
研究・専攻分野 | 人的資源管理論、経営社会学 |
研究テーマ・概要 | 最も力を注いでいるのは整理解雇をめぐる労使紛争に関する研究です。整理解雇をめぐっては、現場の労使や裁判所が実際に発生した問題をめぐって試行錯誤を繰り返してきました。当事者や社会の負担を少しでも軽減するために、経営学が何をなしうるのかという問題意識に根ざした研究をしたいと思います。 |
主な著書・論文 | 【著書】 単著 ・『解雇無効判決後の原職復帰の状況に関する調査研究』労働政策研究・研修機構,2005年(厚生労働省要請研究) 共著 ・Jovanović, M., (2013)ed, Lifestyle in globalization, Megatrend University, Belgrade. (執筆箇所:Lifestyle as a paradigm for post-industrial society: Is there a new lifestyle for Japanese workers? , pp.263-277.) ・神林龍編著(2008)『解雇規制の法と経済』日本評論社 (執筆箇所:第2章「ある整理解雇事件の姿」41-52頁) (執筆箇所:第3章「判例集からみる整理解雇事件」86-115頁) 【論文】 Hirasawa, J. (2016), “Abilities and natures of effort to terminate industrial conflict: Consideration for a Japanese trial concerning economic dismissals” The Nepalese Management Review, Vol, 17 No.1, pp. 1-15.(査読あり) 平澤純子(2015)「裁判における被解雇者」『川口短大紀要』第29号,67-74頁 |
学会活動 | 日本労務学会、日本経営学会、日本キャリアデザイン学会、日独労働法協会 |
メッセージ | せっかく出会えたのですから、勉強のことだけでなくいろんなことを話せるといいですね。 |

所属学科・職位・役職 | ビジネス実務学科 教授 |
経歴 | 【最終学歴】 愛知学院大学大学院商学研究科商学専攻博士課程 単位取得満期退学 博士(学術)桜美林大学 【主な職歴】 中京学院大学経営学部 専任講師・助教授 嘉悦大学経営経済学部 教授 諏訪東京理科大学経営情報学部 教授 東京福祉大学社会福祉学部 教授 川口短期大学ビジネス実務学科 教授 |
担当授業科目 | 経営学総論、経営管理論、経営学、国際経営論、ゼミ(経営学関連分野) |
研究・専攻分野 | 経営史、経営学 |
研究テーマ・概要 | 日本企業の海外進出、外国企業の日本進出 |
主な著書・論文 | 【著書】 (単著) 『国際ビジネス論―日本企業のグローバル戦略と外国企業の日本進出―』唯学書房,平成20年 (編著) 『実学 企業とマネジメント』学文社,平成30年 『歴史に学ぶ経営学』学文社,平成29年 『やさしく学ぶ経営学』学文社,平成27年 『入門 グローバル ビジネス』学文社,平成18年 (共著) 『新企業統治論』税経協会,令和3年4月 『グローバル時代の経営と財務』学文社,平成15年(他あり) 【論文】 (単著) 「トヨタの米国進出とGMとの合弁自動車生産の背景と方法」令和5年12月. 「日本初の電球製造企業の設立と初期困難」川口短期大学紀要,第36号,令和4年12月 「外国自動車企業と日本の自動車企業-1900-1950-」芝浦工業大学,平成27年 「企業の国際化戦略と現地経営の研究」国際総合研究学会,平成22年 『企業の国際化戦略と現地経営の研究―日系企業と外資企業の比較研究―』博士学位請求論文,桜美林大学提出,平成22年 「IBM・日本ワトソンの設立と顧客の変遷―戦前IBMの日本進出とパンチ・カード システムの普及―」愛知学院大学,平成18年 「日本企業の国際経営―日系企業の現地経営―」中京学院大学,平成17年 「日本製造企業の国際経営―キョーセラ在米現地法人の経営―」中京学院大学,平成16年 「日本企業の国際経営―在米日系企業SELの現地経営―」中京学院大学,平成15年 「日本製造企業の海外現地生産」愛知学院大学,平成15年 「ゼネラル・エレクトリック社の日本進出」(2)愛知学院大学,平成15年 「ゼネラル・エレクトリック社の日本進出」(1)愛知学院大学,平成14年 (他あり) |
学会活動 | 経営史学会 経営行動研究学会 国際ビジネス研究学会 |
社会貢献活動 | 長野県茅野市商業観光課推進員 |
メッセージ | 経営学を通して社会を見てください。新しい発見が必ずあります。 |

所属学科・職位・役職 | ビジネス実務学科 教授 |
経歴 | 【最終学歴】 埼玉大学大学院 経済科学研究科経済科学専攻博士後期課程 修了 博士(経済学)埼玉大学 【主な職歴】 KPMG あずさ監査法人 川口短期大学 ビジネス実務学科 専任講師・准教授を経て現職 埼玉学園大学 経済経営学部 兼任講師 埼玉学園大学大学院 経営科学研究科 兼任講師 国立大学法人埼玉大学 経済学部 非常勤講師 |
担当授業科目 | 会計学、経営分析論、財務管理論、専門ゼミ 他 |
研究・専攻分野 | 財務管理、環境金融 |
研究テーマ・概要 | 企業財務とサステナビリティ (1)デジタル環境債に関する研究 (2)有価証券報告書の財務・非財務情報の統合分析 (3)環境保全対策に伴う経済効果の実証分析 (4)ポーター仮説とカーボンデカップリング |
主な著書・論文 | 【著書】 『経済情報リテラシー』泉文堂(2023)共著 『財務・非財務情報の統合分析』泉文堂(2020)単著 『ビジネス情報処理』泉文堂(2020)単著 『信用格付と会社財務・会計制度の新動向』泉文堂(2013)共著 『株式会社の財務・会計の新動向』泉文堂(2011)共著 【論文】 (単著)Haku, RYU(2023)”A Study on the Impact of the New NISA System on ESG Investing”, Journal of Kawaguchi Junior College, Vol.37, pp.27-35. (単著)Haku, RYU(2022)”Fact-finding Analysis on Decarbonization of the Japanese Manufacturing Industry Based on the Decoupling Concept”, Journal of Kawaguchi Junior College, Vol.35, pp.37-44. (単著)劉 博(2022)「鉄鋼業における脱炭素対策の環境性と経済性の両立度の実態分析に関する一考察」日本財務管理学会『年報 財務管理研究』第33号,pp.81-89.(査読付き) (単著)劉 博(2021)「デカップリング概念にもとづく国際比較分析からみた日本経済の脱炭素化の特徴と課題」川口短期大学『川口短大紀要』第35号,pp.25-35. (単著)劉 博(2020)「資源生産性の改善が財務パフォーマンスを高めるのか―「新日鉄住金」の資源循環対策を題材に「ポーター仮説」を検証する」川口短期大学『川口短大紀要』第34号,pp.37-47. (単著)劉 博(2019)「財務・非財務情報の統合分析に関する一考察―2000年代における「新日鉄」の大気汚染防止対策に注目して―」ゆうちょ財団『季刊 個人金融』, pp.115-123. (単著)劉 博(2018)「鉄鋼業の環境効率と財務効果に関する一考察 一「JFEスチール」の事例研究を中心に一」川口短期大学『川口短大紀要』第32号,pp.31-40. (単著)劉 博(2017)「日中鉄鋼業の地球温暖化対策の物量・財務分析に関する一考察 一「新日鉄」と「上海宝鋼」の省エネルギー対策を中心にー」日本財務管理学会『年報 財務管理研究』第28号,pp.190-198.(査読付き) |
学会活動 | 日本財務管理学会 理事 日本信用格付学会 理事 証券経済学会 正会員 環境経営学会 正会員 経営情報学会 正会員 |
社会貢献活動 | 【外部向け講演】 劉 博「2つの「E」を両立させるアプローチ:鉄鋼大手の財務・非財務情報の統合分析と評価」(岡三証券主催 2020年7月) 【メディアからの取材対応】 劉 博 「2024年からはじまる新NISA。企業財務の専門家が非財務情報である環境保護や持続可能性も含めた企業の見方を解説」2023年9月14日 So-gúd(EXIDEA) 劉 博「気候変動対策を支える民間資金」2023年4月11日(火)付 埼玉新聞 コラム「経世済民」 劉 博「炭素デカップリング」2022年3月8日(火)付 埼玉新聞 コラム「経世済民」 劉 博「脱炭素社会の鍵握る鉄鋼業」2021年4月13日(火)付 埼玉新聞 コラム「経世済民」 劉 博「ウィズコロナのESG投資」2020年7月7日(火)付 埼玉新聞 コラム「経世済民」 |
メッセージ | 皆さんもぜひ大学生活を楽しみながら、自分自身の「幸せ」につながる人生目標を見つけ、その実現を目指しましょう。学問は、「世界から【学】び、幸せとは何かを【問】うこと」ですから。 |

所属学科・職位・役職 | ビジネス実務学科 准教授 |
経歴 | 【最終学歴】 上智大学文学部(現・総合人間科学部)教育学科 卒業 文学士 上智大学 【主な職歴】 外資系広告会社マッキャン・ワールドグループのマーケティングリサーチ部門勤務を経て、 ● ユーティルコンサルティング㈱代表取締役社長/㈱ユーティル取締役/エンバイロセルジャパン㈱執行役員(3社とも現・クロスマーケティンググループ) ● GMOリサーチ㈱常務取締役兼チーフマーケティングオフィサー/GMOジャパンマーケットインテリジェンス㈱取締役副社長 ● 楽天リサーチ㈱(現・楽天インサイト㈱)シニアエキスパート ● ㈱サーベイリサーチセンター執行役員 ● Carter JMRN㈱シニアディレクター など、主にマーケティングリサーチ会社の役員を歴任。 情報経営イノベーション専門職大学 超客員教授 学校法人山水学園 非常勤監事 埼玉学園大学 経済経営学部 非常勤講師 (担当科目:マーケティング・リサーチ、消費者行動論) |
担当授業科目 | 【ビジネス実務学科】 マーケティング論、スポーツマーケティング論、ベンチャービジネス論、情報処理Ⅰ・Ⅱ、ゼミⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ(マーケティングリサーチ論) 【こども学科】 ICT活用の理論と方法 |
研究・専攻分野 | マーケティング、マーケティングリサーチ、デジタルマーケティング |
研究テーマ・概要 | 1. 企業における計画的データ収集・分析とマーケティング意思決定の関係性と将来 2. Passive Data(ビッグデータ等)とActive Data(サーベイデータ等)の統合解析による消費者行動の予測精度向上と効果的な広告プロモーション施策実行のための仕組みの構築 |
主な著書・論文 | 【著書】 1. 「多彩な調査ニーズ&顧客リストの活用に有効 DIY(セルフ型)リサーチシステムとは?」『100万社のマーケティング(宣伝会議別冊)』2014年12月号,PP.100-101(単著) 2. 「マーケティング領域の気になる新潮流 旬のトレンド解説 ""聞かない調査手法""」『宣伝会議』2014年1月号, P.45(単著) 3. 「MROCが登場する必然性~社会環境の変化に合わせて、マーケティング情報収集の手段が変容している~」『宣伝会議』2012年5月15日号, PP.83-85(単著) 4. 『オンライン・ソーシャルメディア・リサーチ・ハンドブック ~リサーチャーのためのツールとその技法~』東洋経済新報社, 2011年9月(共同翻訳・全体監修) 【論文】 1. マーケティングリサーチ会社のビジネスモデルと事業成長に関する考察 ―ビジネスドメインの拡張「リサーチ業界からインサイト産業へ」―(『川口短期大学紀要』第37号・2023年12月) 2. Z世代を対象としたマーケティングリサーチの実施課題と若年層向けデータ収集方法の将来展望(『川口短期大学紀要』第36号・2022年12月) 【研究ノート】 日本のマーケティングリサーチ業界における破壊的イノベーションと利益の源泉に関する考察(『川口短期大学紀要』第35号, 2021年12月) |
学会活動 | 日本マーケティング学会、日本マーケティング・リサーチ協会賛助個人会員、日本ブランド経営学会、日本スポーツマネジメント学会、日本消費者行動研究学会 |
社会貢献活動 | 【産業界での実績】 2014年、東証マザーズ(現・東証グロース市場)にGMOリサーチ株式会社の株式を上場 【教育活動】 ● 情報経営イノベーション専門職大学の超客員教授として、起業や会社設立を目指す学生にマーケティングを指導(現任) ● 学校法人山水学園の非常勤監事として、幼保連携型認定こども園事業を推進(現任) ● 上智大学ソフィア経済人倶楽部の運営委員として、大学と産業界の連携による学生のビジネス教育を支援(現任) 【論説】 「論考 ベンチャービジネス論」2023年7月19日(水)付 埼玉新聞 コラム「経世済民」 |
メッセージ | 『マーケティング』は「ファイナンス(経理・財務)」と「アドミニストレーション(管理全般)」とともに企業体を構成する機能であり、業種・職種を問わず、『マーケティング思考』を正しく身につけることによって、ビジネスで大きな成果をあげることができます。 『マーケティング』の学習を通して、自らが主体となって働くことの意義と大切さを学び、物事を自分自身で考える力を養いましょう! |

所属学科・職位・役職 | ビジネス実務学科 准教授 |
経歴 | 【最終学歴】 神奈川大学経済学部貿易学科 卒業 商学士 神奈川大学 【主な職歴】 東京経営短期大学 経営総合学科 非常勤講師(ホテル・観光科目担当) 埼玉学園大学 経済経営学部 経済経営学科 非常勤講師(旅行ビジネス論、世界遺産と観光業、観光ホスピタリティ論、職業指導) Qantas Holidays Limited(AUS、Q.H.International Co.,Ltd.) Silver Fern Holidays Limited Japan(NZ) |
担当授業科目 | エアラインビジネス、エアラインホスピタリティ、ホテルビジネス基礎、テーマパーク論、ホスピタリティ概論、観光交通論、ゼミⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ |
研究・専攻分野 | 【研究】 オーバーツーリズム、地域振興、世界遺産、国際交流、観光ホスピタリティ 【専門分野】 地域活性化、交流型観光 |
研究テーマ・概要 | 【研究テーマ】 サステナブル・ツーリズム(持続可能な観光産業) 【概要】 2021年3月、本学は環境省と「国立公園オフィシャルパートナーシップ」の締結を行い、特別講義・フィールドワーク・産学連携に役立てています。これは全国の大学機関で2校目となるもので、その自然環境保護と観光促進を両輪で学ぶ先取的な取組みに対し、外部から高い評価を受けています。脱炭素・地球温暖化防止に寄与し持続可能な観光の在り方を明らかにしながら、オリジナリティのある多彩な観光分野の探究により、学習成果を生み続けます。 |
主な著書・論文 | 【論文】 ・観光産業への人材輩出DXの実証実験(日本観光研究学会 第38回全国大会・2023年12月) ・観光学に環境保護を反映する一考察(日本観光研究学会 第37回全国大会・2022年12月) ・観光地域振興に資する政策についての一考察(『川口短期大学紀要』第36号・2022年12月,査読あり) ・日本のウェブサイトを中国国内へ情報発信する方法(観光情報学会,第15回観光情報学会全国大会in九州・2018年5月) ・「在宅通訳者」を活用して「地方創生」と「テレワーク」の推進を行う(日本観光研究学会 第32回全国大会・2017年12月) 【研究ノート】 ・環境省との「国立公園オフィシャルパートナーシップ」導入の事例報告(『川口短期大学紀要』第35号・2021年12月) ・アフターコロナでインバウンドが力強く再生するための考察(『川口短期大学紀要』第34号・2020年12月) |
学会活動 | ・日本観光研究学会 ・一般社団法人日本スポーツツーリズム推進機構(JSTA) |
社会貢献活動 | 【観光・環境関連への貢献】 ・観光庁「国立公園オフィシャルパートナーシッププログラム」に基づく環境保護活動と産学連携(箱根温泉旅館ホテル協同組合、株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド、日産自動車株式会社) ・観光庁に登録された専門家活動 「インバウンドの地方誘客促進のための専門家」 「観光地域づくり法人における外部専門人材の専門家」 ・公益社団法人日本観光振興協会に登録された専門講師 「研修ナビ」講師 【メディアからの取材対応】(過去4年分) 埼玉新聞にコラム掲載(就活DXで観光人財育成を)2023年12月14日 埼玉新聞にコラム掲載(自信と誇りを取り戻す観光の力)2023年6月20日 埼玉新聞にコラム掲載(観光予報によるゲームチェンジ)2022年7月12日 埼玉新聞にコラム掲載(環境保護と脱炭素の賢い選択)2021年12月14日 埼玉新聞にコラム掲載(環境と観光を両輪で学ぼう)2021年5月11日 埼玉新聞にコラム掲載(前程万里、五輪と観光)2020年10月7日 |
メッセージ | 各講義では観光の持つ多彩な魅力を理解するために受講生のやる気を引き出し興味を持続させる多くの工夫を取り入れています。 さらにフィールドワーク、ゲスト講師の招聘、企業説明会の誘致等で多面的に学び、その結果として観光業界への志望へと立体化していきます。最終目標である「観光に強い川短」へのブランド化を目指す多方面で現場経験を積んだ講師の実益に溢れた講義により自己肯定感を高めていきます。 最新情報に基づく近未来の予測、さらにDX(デジタルトランスフォーメーション)やAIを取り入れたアプローチで、今後の日本を支えていく基幹産業となる「持続可能な観光(サステナブル・ツーリズム)」への魅力に触れてください。 |