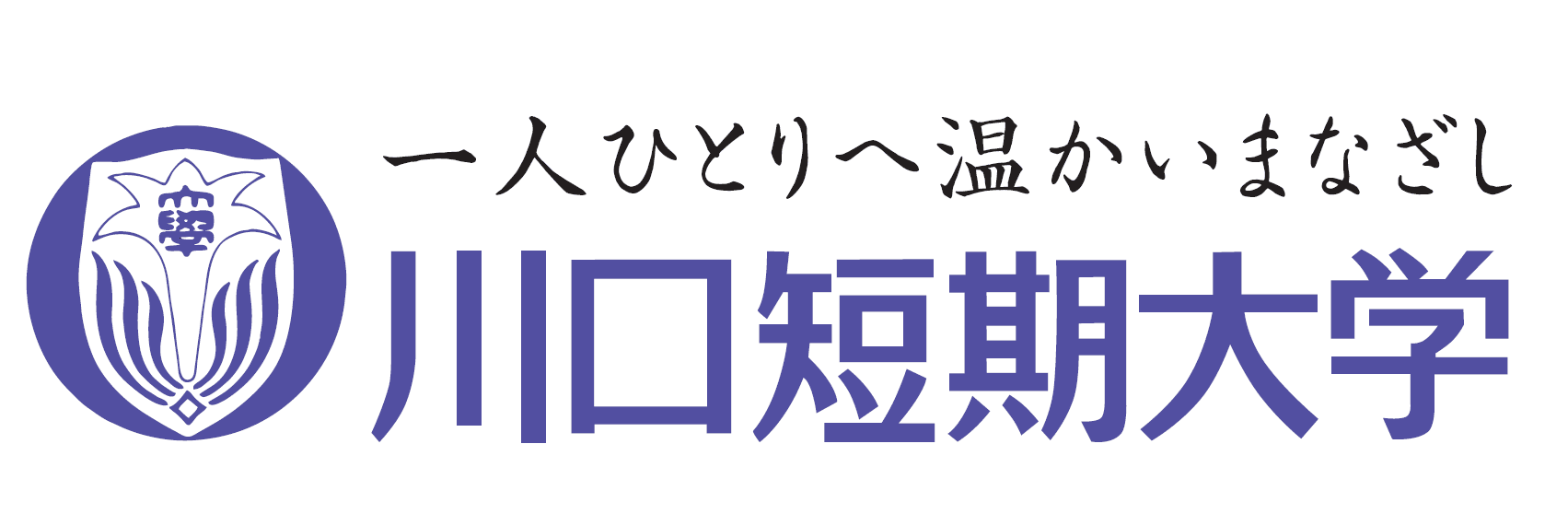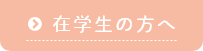【初めての乳児室での授業】赤ちゃん人形を抱っこ、おんぶしました
2024-04-30
カテゴリ:活動の紹介-こども学科
こども学科1年生は、「乳児保育」の授業において、乳児室デビューを飾りました。
授業内容は赤ちゃん人形での抱っこ、おんぶの実践です。
前回の授業で「出産」を学んだので、生まれてきた新生児の身体の大きさを自分たちの五感で体感してみました。


その後、抱っこ紐やおんぶ紐を使い、その方法を実践を通して学びました。
学生たちは、抱っこ紐おんぶ紐の装着方法に悪戦苦闘しましたが、協力し合って全員が抱っこまたはおんぶをすることができました。
みんな、自然と笑顔になっていました。


学生の感想
- 赤ちゃんの人形だとしても3kgって思っていたよりも重くて、命の重さを感じた。
- 横抱き、たて抱きがあること、そのやり方を実践することができた。赤ちゃんがびっくりしないように声をかけて抱っこすることも大切であることを知った。
- 赤ちゃんを抱くときには手を洗う、赤ちゃんが寝る所、食べるところには不衛生なものは置かない、抱っこ紐は正確に装着して使うなど当たり前だけどすごく大切なことをしっかりと守るようにしたいです。